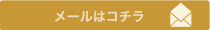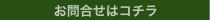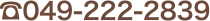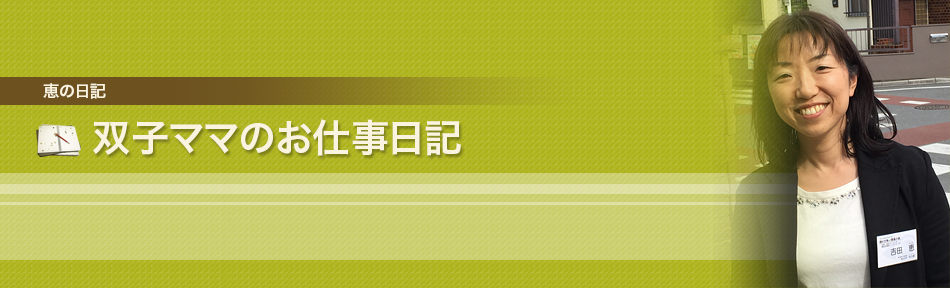最近怒涛の忙しさだったのですが、
ようやく一仕事片付いてブログを書く余裕が出来ました(笑)
何で忙しかったかというと、今度新築する物件の
建築確認申請の準備です。
今年4月に、建築基準法が改正され、
これまでは長期優良住宅やフラット35など、追加の申請をするときだけ
審査していたような省エネ性能や耐震性能などを、
全ての建物で審査しなければならなくなったんです。
さらに、追加で提出しなければならない図面も
いろいろ増えてしまって…(一一”)
改正された4月以降、幸い(?)そういった審査の特例が適用される
平屋建ての申請が続いていたので、
申請書類の準備は従来通りだったのですが、
今回、今年初で2階建ての申請で
初めての改正建築基準法対応の申請準備となったため、
いろいろと確認作業が多く、正直かなり大変でした(^^;
やっと書類を一通りそろえて、審査機関に提出したのですが・・・
でも実は本当の問題はここから(+_+)
これまで省エネなどの審査が必要なかったものまで
全て審査をするということは、当然審査機関の仕事量が増えるということ。
これまで確認申請を提出すれば、おおよそ10日から遅くも2週間程度で、
審査に入り、訂正等を経て、20日~1か月程度で
審査が終わるものが多かったのですが、
今は提出してから、受付をして担当者が審査に入るまでに1か月半!
これまでも審査に時間がかかっていた長期優良住宅などについては、
受付までで2カ月半かかるというんです(+_+)
「工期に問題があるような場合は、他の審査機関へ移っていただいても・・・」
そんな連絡を受けましたが、
こんな状態で他が空いているわけがないですよね(^^;
多少の差はあれど、どこも同じような状態。
審査機関に電話をして、事情を聞いたら、逆に
「私たちも連日残業して進めてるんですが・・・」
と、かなり愚痴の入ったご説明がありました(~_~;)
確かに、省エネ関連、さらに耐震性などの構造関連の書類の枚数、
すごいんですよ!
省エネの計算書や確認資料だけで50枚越え、
構造計算書に至っては、今回の物件でも448ページもあるんですから!
それを図面の整合性を一つ一つ確認していくって、
とんでもない作業量です。
でもね・・・審査機関の方の苦労はものすごくわかりますが、
それで着工が遅れてしまうのも、本当に困ります。
申請した物から一つでも変更があると、
計算式が変わってしまったりするので、今度は変更申請が必要になってしまうため、
もう変更が出ないように打合せを詰めてからでないと
下手に書類を作成することができないので、
先行して申請しておく、というわけにもいかないのが厄介な所。
徐々に作業に慣れもするでしょうし、対策もされてくるのだとは思いますが、
検査機関の絶対数が急に増えることはありえないので、
今後申請には、相当の時間がかかるとあらかじめ覚悟しておいた方が
よいだろうとも言われています。
例えば賃貸の更新時期であるとか、
お子様の入学とか、
ご入居までに何かしらの期限を持っていらっしゃる方は、
これまで以上にかなり余裕を持って家づくりに取り組まれることを
心からおすすめします。
今回の申請も、出したはいいけれど、受付してもらえるのは年明け?
「検査員さん頑張ってください!」
としか言えないのが、本当に辛いです(一一”)